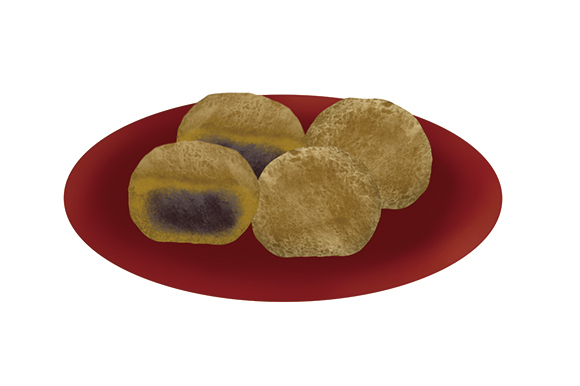厄除けは地域によってさまざまな風習があります。
近年、厄除けのお返しとして厄除け饅頭を贈られる方も多くなってきました。
お返しとして厄除け饅頭をお考えの方へ、熨斗や水引についてまとめました。
本来の厄年の意味も含めてわかりやすくまとめていますので是非最後まで読んでみてくださいね。
■厄除け饅頭を配る際の熨斗
ここで説明しているのは、あくまで厄年の方がご近所へ振るまう用の熨斗についてになります。
まず厄除け饅頭へかける熨斗についてですが、表書きは「厄除祈願」「厄祝」と書きます。
”厄”というと少しマイナスなイメージを持たれる方も多いと思いますが、
厄年は”この年齢を無事に迎えられた”という意味も込められた”お祝い”にあたります。
なので表書きには「厄祝」とされてOKです。
そして名前は苗字だけではなく、フルネームで記入しましょう。
なぜならその家の人全員が”厄年”になった訳ではなく、あくまで厄年は個人のお祝いになるからです。
■熨斗の水引は蝶結び?
前項でもお伝えした通り、厄年は「お祝い」にあたるので、水引は蝶結びで正解です。
蝶結びは慶事に利用される水引の結び方で、簡単に解ける結び方をしていますよね。
これは何度も結び直せることから「何度あってもよい」お祝い事として使われます。
「厄年なんて何回もきてほしくないのにどうして?」
と疑問に思われる方もいるかもしれません。
しかし厄年、特に本厄には昔から「重要な役割を持つ年」などと言われ、喜ばしい事とされていました。
厄年は、体調を崩したり、災難にあいやすいなどの言い伝えばかりが注目されてきましたが、良い意味でも、悪い意味でも「人生にとって変化が訪れやすい年」という事には変わりありません。
厄除け饅頭を配り、食べてもらうことで、厄を消し去る効果があるとされている事から、厄除け饅頭は厄払いには欠かせないものとなりました。
この年齢を無事に迎えられた事に感謝して、体調などに気を付けつつ過ごせるよう盛大にお祝いされると良いですね。
■自分の厄年はいつ?
厄除け饅頭について色々お話しましたが、何回も訪れる厄年・・・男性でも女性でも自分がいつ厄年にあたるのか気になりませんか?
厄年と言われる年齢は”数え年”でみます。
数え年とは生まれた年を「1」とする数え方で、誕生日ではなくお正月で1つ年をとります。
なので12月31日生まれの赤ちゃんは、生まれた日を1歳とし、次の日のお正月で2歳になるということですね。
厄年は男性で25歳・42歳・61歳。
女性で19歳・33歳・37歳・61歳とされています。
特に男性の42歳と女性の33歳は”一生のうちに厄が最も降りかかりやすい年”である大厄とされるため、できるだけ謹んで静かに暮らすのが良いとされています。
ちなみに大厄のまえの年を前厄、あとの年を後厄と呼び、前後合わせて3年間は体調や災難にあわぬよう静かに過ごした方良いそうです。
■まとめ
マイナスなイメージがある厄年ですが、厄年とはもともと”お祝い事”であるという事を忘れずに準備をすると良いと思います。
厄除け饅頭を贈る際は「おかげさまで、厄払いも無事に終える事ができました」と一言添えると、貰う側としても嬉しい気持ちになりますね。
厄年だからといって何か起こるというよりは、皆が気を付けるべき身体のサインがでやすい時期だととらえ、いつも以上に身体をいたわりながら、平穏に過ごすことを心がけるといいですね。